武蔵野アートハイクにしてやられた——“わからなさ”が癖になるサイクリング|武蔵野 ART HIKE 体験記
武蔵野アートハイク(12月07日迄開催)に行ってきた。自転車で回って、スタンプラリーを全部コンプリート。正直、最初は“現代アートを巡る冒険”みたいなものを想像していた。でも実際に体験してみると、想像していた「展示」とはまるで違った。
派手さも、目を奪うような造形もない。代わりにあったのは、風景と溶け合って静かに佇む“違和感”だった。
最初の作品を見つけたとき、「あ、これがそうなのか」と少し戸惑う。言い表しようがない。むしろ、“当たり前の中にひっそりある、とても当たり前ではないモノ”という感じだった。
たぶん、それがこのアートハイクの本質なんだと思う。ここでは「現代アートを見る」というより、“日本人のふるさとのような風景の中で現代アートに気づく”体験が起きていた。
さっきの現代アートはなんだったの???というモヤモヤをおしゃべりしながら、三ヶ島の秋の彩り豊かな景色と空気を味わうこと自体が「武蔵野アートハイク」なのかもしれない。面白い企画だと感じる。今から来年の作品が楽しみだ。
ちなみにこの三ヶ島コースは、所沢店の相田店長がルート作成を手伝っている。

武蔵野を走る——現代アートが風景に溶けている違和感
ペダルを踏みながら、武蔵野の道をゆっくり進む。秋の空気は澄んでいて、雑木林の匂いが風に混じる。バイパスをわたり、コスモスが咲く小径を抜け、三ヶ島のほうへ入っていくと、都会の喧騒とは違う“音の少なさ”に気づく。
現代アートは、その静けさの中に溶け込んでいた。気を抜いていると通り過ぎてしまうような場所に、さりげなく置かれている。
「これがアートなの?」と立ち止まると、頭の中が混乱してくる。作家さんの想いや意図を必死に想像し、答えを探すが見つからない。
“わからない”のに惹かれ、取り憑かれてしまう
最初のうちは、意図がまるで掴めない。「なぜここに?」「何を表してるの?」そんな疑問ばかりが頭に浮かぶ。
でも、自転車で移動しながら見ていると、だんだん不思議な感覚になってくる。どの現代アートも、説明されない余白をたっぷり残している。わからない。だけど、なんか気になる。その“わからなさ”が、じわじわと心の奥に残る。

現代アートは、感動させるよりも考えさせることを狙っている。つまり、現代アートは「答え」ではなく「問い」のようなもの。小さな疑問をこちらに渡し、持ち帰らせる。武蔵野アートハイクは、その仕組みをルート全体で体験させてくる。
処理しきれない情報が頭の中で大混乱。作家さん達にまんまとしてやられた感じがして実に愉快。こんなに考えさせられるサイクリング体験は、正直生まれて初めてだ。
和田園で感じた、“暮らしそのものが現代アート”

武蔵野アートハイクの中で、特に心に残ったのが和田園だった。広がる茶畑の畝(うね)が、それ自体でひとつの造形のように見える。風が通るたびに葉が光を返し、畑全体が呼吸するようだった。
そこで腰を下ろし、たくさん話をした。茶を育てること、摘むこと、淹れること——どれもが穏やかに語られる。和田さんの話は、技や知識というより“暮らしの時間”であり、まさに「研ぎ澄まされた感性」だった。お茶と人との長い歴史が息づいている。
そのとき思った。奇抜な造形や発想だけが現代アートなのではなく、人が時間をかけて土地と関わってきたこと自体が、すでに芸術に値するのではないかと。
和田園で味わったお茶の温度、香り、あまみ、風の匂い、会話の間(ま)まで含めて、すべてが現代アートだった。“作品を見る”から“暮らしに触れる”、そして“プロの仕事に触れる”へ。この転換が、僕の中で現代アートという言葉をあたたかく書き換えた瞬間だった。

現代アートは“考える時間”をつくる装置
アートハイクを終えて数日が経っても、「現代アートってなんだ?」という問いが頭から離れない。仕事をしていても、ふとあの時の風景が浮かんでくる。雑木林の奥の鉄の影、風に揺れる草の音、そして“現代アートがわからなかった自分”。
その全部が、ひとつの作品のようにまとまって襲ってくる。たぶん現代アートって、鑑賞者の頭の中で延命する。展示を見終わってからが、むしろ本番だ。
「してやられた」——現代アートの後遺症

正直に言えば、樹樹に展示されているアートはアートと呼びたくない内容に思えた(ここでは理由は触れない)。それでも、あの大胆さは強烈に記憶に残った。——これが現代アートってやつか、とつい笑ってしまう。ぜひみに行ってほしい。
他の作品も結局よくわからなかったが、なんと言うか、完全にしてやられた。
それぞれで感じた退屈さ、戸惑い、違和感、疑問。その全部が、今になって効いてきている。“わからなかったという体験”がずっと頭の中で続き、話をしていても話題の中心にいる。
現代アートの怖いところ(≒ 癖になる面白さ)はここだと思う。一見、何も起きていないようで、頭の中では確実に何かが動き始めている。そんな状態にいる自分たちが、悔しいくらいに面白い。
ただの風景が、やけに心に残った。

さとやまの小道を抜けて、谷戸の田んぼに出た瞬間に思った。「なんだこれ、アートじゃないのにアートみたいだな」と。
風がやわらかくて、トンビが空をくるくると回っていて、田んぼの水面が空を映してる。誰かが作った作品じゃないのに、ちゃんと構図があって、色があって、空気がある。
武蔵野アートハイクの面白さって、もしかしたらここにあるのかもしれない。作品を探していたつもりが、気づいたら風景のほうを見てる。“展示の外側”に、いちばん豊かな魅力がある。
現代アートが人にモヤモヤを投げるなら、武蔵野の風景はもっと静かに語りかけてくる。
「三ヶ島の秋の風景、いいだろ? でも、いいのは秋だけじゃないぜ。」って。
みなさんへ——あなたも“現代アートにしてやられて”ほしい
このブログを読んでくれた人には、ぜひ一度、武蔵野アートハイクを自転車で回ってみてほしい。派手な展示はない。感動的なドラマもない。けれど、風景の中をゆっくり走りながら、「これが現代アート?」「何を表してる?」と小さな「モヤモヤ」を繰り返すうちに、気づけば、自分の中で何かが動き出し、ちょっとした混乱の中に置かれる。
僕と同じように、“現代アートってなんだ?”という問いが離れなくなるかもしれない。でもそれがいい。自転車を漕ぎながら考えさせられてしまい、自転車を漕ぎながら話が盛り上がること自体が、楽しい。なので、ソロではなくぜひ家族や友人達と一緒に出かけてほしい。
あとがき——考え続けてしまう、それが現代アートの罠
帰ってからも、ふとした瞬間に思い出す。あの作品、結局なんだったんだろう。
歯磨きしてても、信号待ちしてても、急に脳内に出てくる。たぶん、まだ武蔵野アートハイクのポタリングは終わってない。
武蔵野アートハイクの作品はどれも派手じゃないし、「すげぇ!」みたいな瞬間もない。
でもあとからじわじわ効いてくる。何かを問われてるようだけど、正解がわからない。
そのもどかしさが、面白い。
「アートって何?」なんて難しいことはわからないけど、三ヶ島の風景はとても素敵だと思った。それだけでもう、十分アートにしてやられてる。
結論:作家さんの想いや意図を想像しながらおしゃべりする「ポタリング」として武蔵野アートハイクは最高
武蔵野アートハイクは、エンタメではない。でも、仲間とおしゃべりしながら楽しむ一日サイクリングとしては最高だ。“わからなさ”の中に立ち止まり、“風景と現代アートの境界”を感じながら走る。互いの「わからなさ加減」を笑い合う。
武蔵野・三ヶ島の田舎道、雑木林の木漏れ日。その中での時間こそが、現代アートが仕掛けた一番大きな作品なんだと思う。
結局、僕らは現代アートにしてやられた。でも、悪くない。楽しい。懐かしさを感じる風景画のような三ヶ島エリアで、この後遺症をみなさんも楽しんでみては?
👉 武蔵野アートハイク公式サイト
👉 武蔵野アートハイク公式 サイクリングコース Google Map
👉 武蔵野アートハイク公式 サイクリングルートGPXファイル
👉 おしゃべりしながらライドを楽しむなら… SENA(セナ) BiKom 20 がおすすめ!



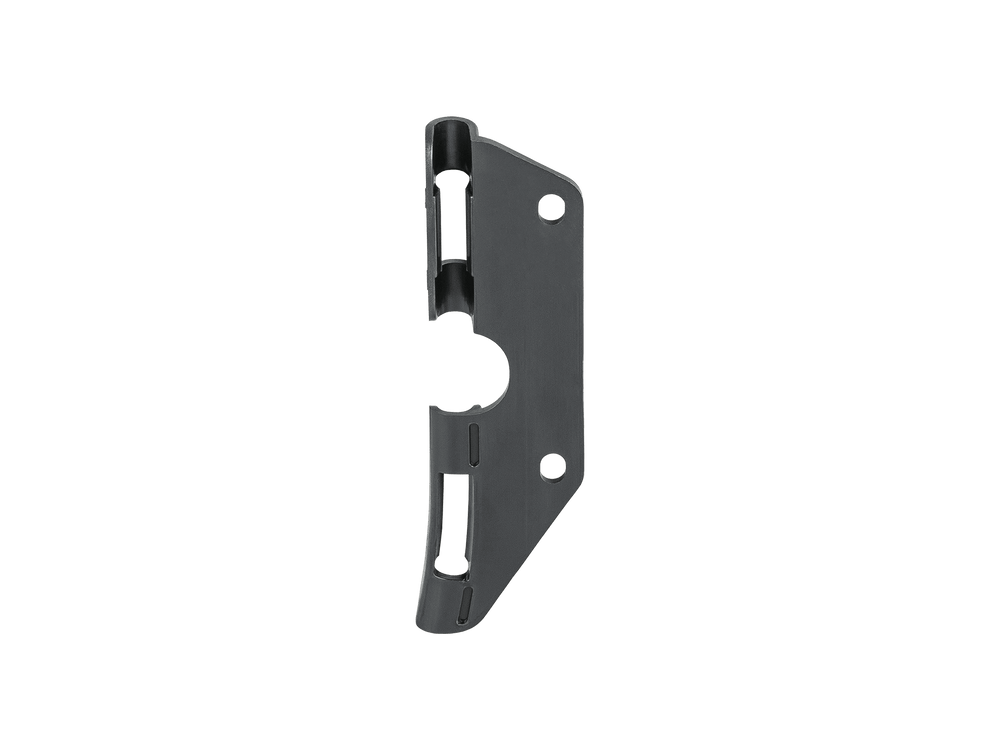















































この記事が参考になったら、ぜひコメントをどうぞ!