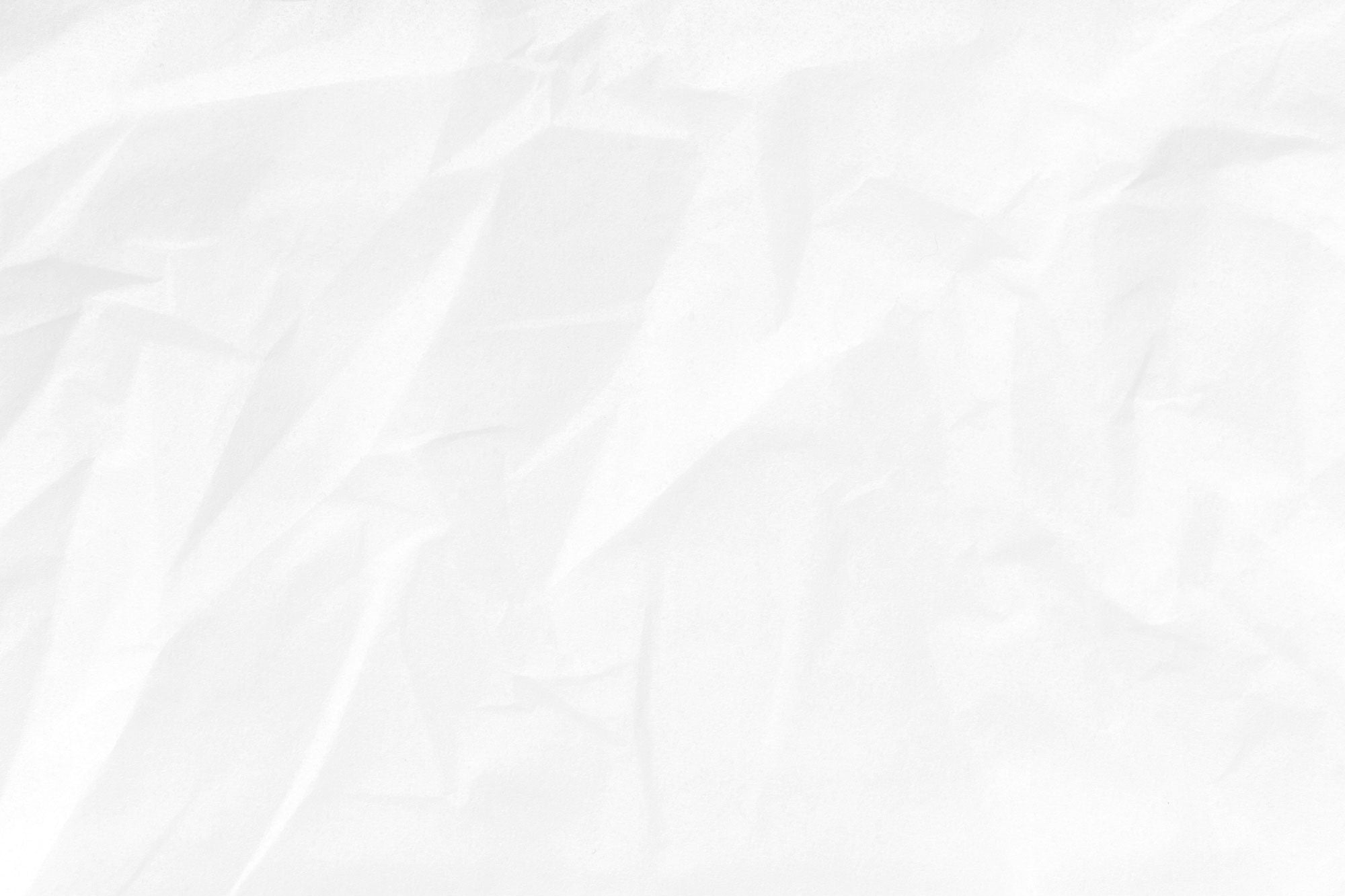マドン9でも輪行できる!?スタッフが実践した裏技を公開しちゃいます!
使用した用品一式:
 今回使用した用品はこちらになります。
キズが不安な方はフレームカバーを多めに使うことをおすすめします。
今回使用した用品はこちらになります。
キズが不安な方はフレームカバーを多めに使うことをおすすめします。
 今回使用した用品はこちらになります。
キズが不安な方はフレームカバーを多めに使うことをおすすめします。
今回使用した用品はこちらになります。
キズが不安な方はフレームカバーを多めに使うことをおすすめします。
- オーストリッチ L-100
- オーストリッチ エンドスタンド 110mm用
- オーストリッチ チェーンハンガー
- オーストリッチ フレームカバー(4枚入)
- オーストリッチ フリーカバー(ロード用)
- オーストリッチ 肩パッド15
- 包装用紐(1500mm分)
マドン9の輪行方法裏ザワはこんな流れ
フレームとヴェクターウィングの養生、ハンドルが切れないようにするためのワザ
外したホイールをフレームに左右から密着させて固定する、ここまでは輪行の基本的な作業の一つになります。ただマドン9のエアロフレームの場合、フレームのシャープな部分がホイールに局部的にがっつり当たってしまい、そのままでは傷つけてしまう恐れがあります。 それ以外にも、ハンドルを切ると展開するヴェクターウィングなどのパーツもそのままだとキズ、最悪は破損の恐れがあります。そのため、フレームをいかに保護するかがとても大切になってきます。 また、ヴェクターウィングはハンドルを切ると広がるため、ハンドルを切れないようにする工夫が必要です。そこの裏技は後半でご紹介します。フレームカバーを思い切ってカットして使用する
 半分に分割し繋ぎ合わせることでフレーム取付をしやすくします。
半分に分割し繋ぎ合わせることでフレーム取付をしやすくします。手順①
ハブ軸が当たる部分の養生方法 ホイールのハブ軸が当たるトップチューブとシートステーの境目に半分に切ったカバーを縦に繋ぎ合わせ、一枚分取り付けます。
この際、接着面の部分をハブ軸に当たる箇所に持って行くことで、持ち運び時にずれるのを防いでくれます。
ホイールのハブ軸が当たるトップチューブとシートステーの境目に半分に切ったカバーを縦に繋ぎ合わせ、一枚分取り付けます。
この際、接着面の部分をハブ軸に当たる箇所に持って行くことで、持ち運び時にずれるのを防いでくれます。
手順②
 もう一枚分割したフレームカバーを①の上から覆うように巻いていきます。
この時も、接着面をハブ軸が当たる位置に持って行くことで、固定力やクッション性をあげてくれます。
ホイールを重ねると・・・・・
もう一枚分割したフレームカバーを①の上から覆うように巻いていきます。
この時も、接着面をハブ軸が当たる位置に持って行くことで、固定力やクッション性をあげてくれます。
ホイールを重ねると・・・・・
 ホイールを重ねると写真のような状態になります。
今回のマドン9輪行でもっとも重要な部分でもあるため、しっかりカバーは固定します。
また、保護力を高めるのであれば、この上からタオルを被せてあげるという方法もありかもしれません。
ホイールを重ねる際、クイックレリースを外した状態で作業したほうが固定しやすくなります。
ホイールを重ねると写真のような状態になります。
今回のマドン9輪行でもっとも重要な部分でもあるため、しっかりカバーは固定します。
また、保護力を高めるのであれば、この上からタオルを被せてあげるという方法もありかもしれません。
ホイールを重ねる際、クイックレリースを外した状態で作業したほうが固定しやすくなります。
外したクイックレリースはその場に置かず、すぐバッグなどに閉まっておくのがオススメです!
手順③
ヴェクターウィング部分の養生 今度はヘッドチューブにあるヴェクターウィングの保護。
半分に切ったカバー1枚分を縦状にし、接着面をブレーキ側にして巻いていきます。
ハンドルを切った際に展開するため、ちょっとでも開いた際にどこかに引っかかって破損するかもしれませんので、しっかり固定。
工具があればヴェクターウィング自体を外しておくという方法もありますが、その際はブレーキパーツがフレームに当たる可能性があるので、パーツが当たる箇所を保護しておくと良いかもしれません。
今度はヘッドチューブにあるヴェクターウィングの保護。
半分に切ったカバー1枚分を縦状にし、接着面をブレーキ側にして巻いていきます。
ハンドルを切った際に展開するため、ちょっとでも開いた際にどこかに引っかかって破損するかもしれませんので、しっかり固定。
工具があればヴェクターウィング自体を外しておくという方法もありますが、その際はブレーキパーツがフレームに当たる可能性があるので、パーツが当たる箇所を保護しておくと良いかもしれません。
手順④
ダウンチューブとホイールが当たる部分の養生⑴ その他にタオル等でも代用は出来ます。
その他にタオル等でも代用は出来ます。手順⑤
ダウンチューブとホイールが当たる部分の養生⑵ 残りのカバーはトップチューブに取り付けます。
ここもタイヤとリムが当たる箇所に設置し、しっかり固定してあげます。
固定が弱いとずれてしまうので注意。
残りのカバーはトップチューブに取り付けます。
ここもタイヤとリムが当たる箇所に設置し、しっかり固定してあげます。
固定が弱いとずれてしまうので注意。
手順⑥
ヴェクターウィングが広がらないようにハンドルを固定する 重要な個所の一つなので、しっかり固定
重要な個所の一つなので、しっかり固定 袋に収納した状態です。
ハンドル部分の関係で横幅は広がるものの、移動の際は特に支障はなく、電車内での置き場所を確保すれば問題ない状態です。
ただ、はみ出しやすいので、しっかり生地を伸ばし、フロントフォークなどもしっかり覆うようにしてください。
輪行袋を収納する袋をフロントフォークに差しておくと、キズ防止の保護になります。
袋に収納した状態です。
ハンドル部分の関係で横幅は広がるものの、移動の際は特に支障はなく、電車内での置き場所を確保すれば問題ない状態です。
ただ、はみ出しやすいので、しっかり生地を伸ばし、フロントフォークなどもしっかり覆うようにしてください。
輪行袋を収納する袋をフロントフォークに差しておくと、キズ防止の保護になります。
まとめ
 いかがだったでしょうか?
せっかく買ったのに輪行できない・・・・っと悩まれていた方に向けて、少しでも楽しめるように色々と考えて実践してみました。
まだまだ工夫次第で、もっと楽にできる方法があるかも知れませんが、もしご参考になればと思います。
もし分からないことがあれば、ぜひ店頭のスタッフにお尋ねください。
(※あくまで参考的な作業行程になります。メーカー公式ではないので、行なう際は自己責任になりますのでご了承ください。)
いかがだったでしょうか?
せっかく買ったのに輪行できない・・・・っと悩まれていた方に向けて、少しでも楽しめるように色々と考えて実践してみました。
まだまだ工夫次第で、もっと楽にできる方法があるかも知れませんが、もしご参考になればと思います。
もし分からないことがあれば、ぜひ店頭のスタッフにお尋ねください。
(※あくまで参考的な作業行程になります。メーカー公式ではないので、行なう際は自己責任になりますのでご了承ください。)
もっと見る:
スタッフ一押し!