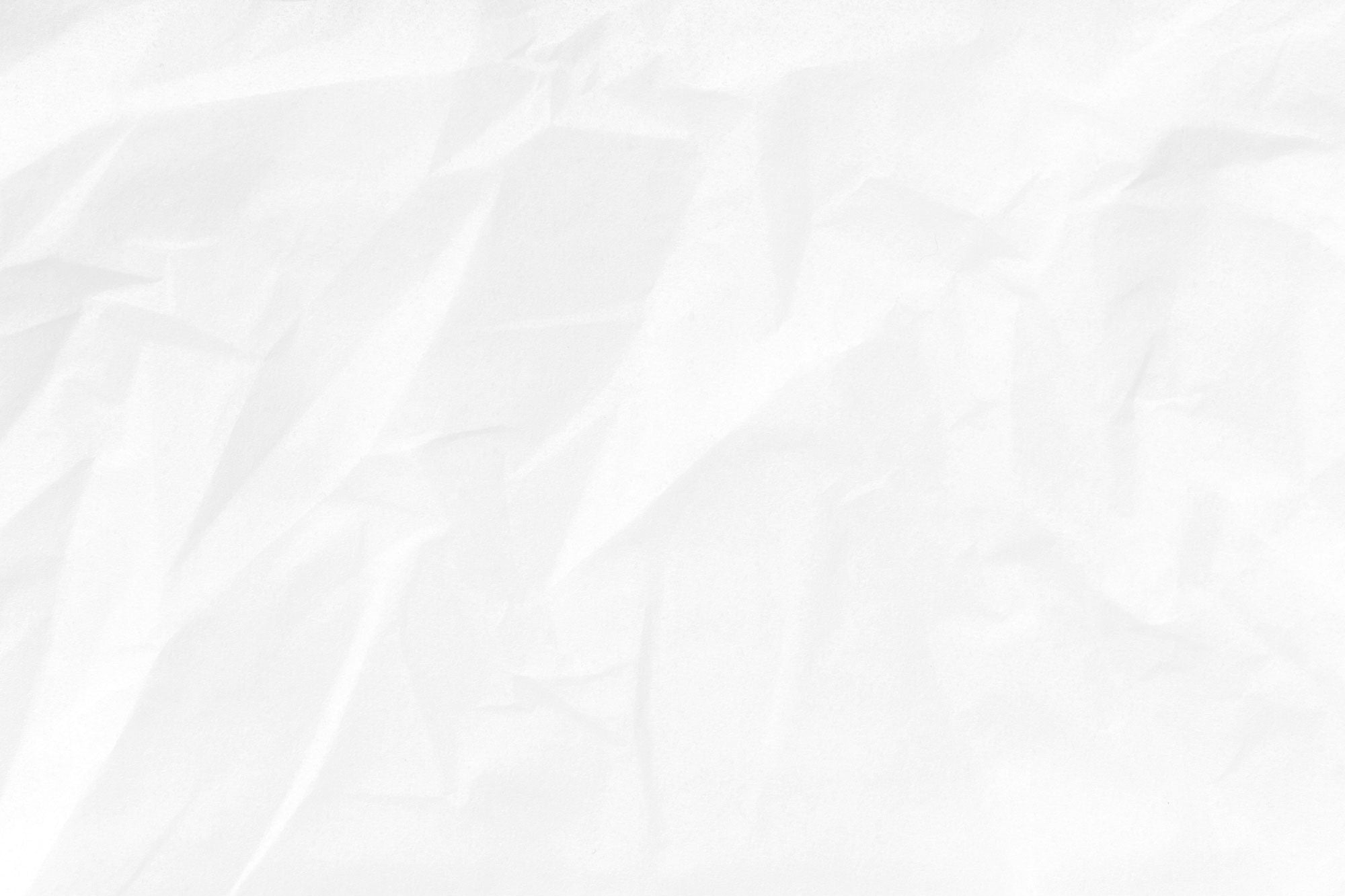新型 Line Pro 30を設計から読み解く|23.5mmリムのしなやかさ×Rapid Drive 108

新型 Line Pro 30 / Line Comp 30|快適さと耐久の新バランス。
正直に言うと、以前は(他社ですが)高かったのにすぐ割れてしまったカーボンリムにがっかりした経験もありました。でもボントレガーのカーボンリムは別物。とにかくタフで、日常的にガンガン使っても大きな問題が起きません。そんな理由で長年Line Pro 30を愛用してきた私・西村です。
今回はまだ未試乗の段階ですが、公開されている情報や設計の理屈から、新作Line Pro 30の狙いを読み解きます。キーワードは23.5mmリム、前後で+13%/+11%のしなやかさ、そして局所補強とオフセットスポークベッドで強さをキープしながらの柔らかさ。つまり「快適さと強度の両立」をどう作り込んでいるのか?を見ていきます。
【NEW】Line Pro 30(カーボン)とLine Comp 30(アルミ)が同時リリース。どちらも27.5 / 29をラインアップ。
1. 総論
結論:新型Line Pro 30は、23.5mmの浅めリムにすることで縦方向のしなやかさを前+13%、後+11%に調整。そのうえでスポーク周りの補強とオフセットスポークベッドで横剛性と強度をしっかり確保。結果、細かい突き上げの角を丸めてくれて、接地感が途切れにくく、長い区間でも集中力を保ちやすい足回りが期待できます。
- しなやかさ=性質(縦にたわむよう設計)。いなし=挙動(衝撃を短い時間で逃がす動き)。
- 「浅い=弱い」とは限らない。厚みをつける場所とスポークの角度で剛性を作れる。
- 駆動はRapid Drive 108(3.3°)。反応の速さは相変わらず優秀。
- TLR設計は広いタイヤウェルとなめらかなビードシートでセットアップが速い。強化フックウォールはピンチ耐性を底上げ。
- 保証は生涯保証+Carbon Care(2年)+30日満足保証。安心して攻められるサポート付き。
2. 用語整理:「しなやかさ」と「いなし」
しなやかさはホイールが縦にしなる性質のこと。段差を「ドン!」と一気に受けず、「ググッ」と少しだけ時間をかけて和らげるイメージです。
いなしはその結果として起こる受け流しの挙動。卵をキャッチするときに手を引くのと同じで、衝撃の角が丸まり、手首や前腕の刺さる感覚が減ります。
- しなやかさ=性質(縦にしなるよう作ってある)
- いなし=結果(衝撃を短い時間でやわらげる)
重要なのは、横方向まで柔らかくする必要はないこと。縦はしなやか、横はしっかり、が理想です。そのためにスポークオフセットや局所補強で横剛性や耐久性をきちんと確保しています。
3. 23.5mmリムが生む“縦のしなやかさ”

新作ではリムの高さを23.5mmに。これにより縦方向の硬さを和らげ、前後で+13%/+11%のしなやかさを確保したと公表されています。結果、小刻みな突き上げや根っこで手首の刺さりが減り、接地の安定感とライン維持に効果が期待できます。
もちろん実際の乗り味は空気圧やタイヤの構造、インサートやサス設定で変わります。ただ、設計の方向性としては「快適さ=速さを長く保つ」方向に振っているのは間違いないでしょう。
※リムハイト23.5mmというメーカーからの情報ではありますが、23.5mmと記載したイラスト上の計測位置は、私の憶測で記載してあります。間違っていたらごめんなさい。
4. 局所補強とオフセット:強さの配分設計
「浅い=弱い」ではありません。大切なのはどこを厚くして、どこをしならせるかのバランスです。新作ではスポーク付近の補強、フックウォールの厚み増、さらにオフセットスポークベッドでテンションを最適化。これにより縦方向のしなやかさと横剛性を同居させています。
- 局所補強:スポーク穴周りの割れや剥離リスクを低減。
- オフセット:左右テンション差を縮めて横の安定を確保。
- フックウォール強化:低圧でのピンチ(リム打ち)に耐える。
全体の剛性をただ盛るのではなく、必要なところにだけ強さを配分する。結果、荒れたセクションでも「怖くない速さ」で走れるようになります。
5. Rapid Drive 108(3.3°):遅れないハブ
かかりは108ポイント=3.3°。ペダルをちょっと踏んだだけで駆動がつながり、根っこ手前の半コギやライン修正でも遅れません。音は控えめですが、仕事は早い。この“即応性”はしなやかな足回りと相性が良さそうです。
さらにLine Pro 30はストレートプルスポークを採用。Jベンドのような肘の応力集中がなく、力がハブ→スポーク→リムへまっすぐ流れやすい。つまり駆動が立ち上がった瞬間でもテンションのバラつきが出にくく、リムがブレにくい設計です。
6. TLR&フックウォール:セットアップの速さと安心感
新旧モデルの断面図をじっくりと見比べると、タイヤウェルが緩やかで、ビードシートへのリードインがなめらかになった印象を受けます。さらにビードシート周りの曲率(R)や角度を微妙に変更(最適化)したことで、初期加圧からビードが早く密着=シーリングが進みやすい形状になっていそうです。結果、フロアポンプでも最初の「ポンッ」としたポップに届きやすい=セットアップが速い...そんな印象を持ちました。
また、標準でTLRリムストリップが付属。スポーク穴を一気に密封してリム内を整えるので、空気漏れのリスクが減り、安定してビードが座ります。
作業のコツ:ビードをしっかりウェルに落とす → 石鹸水を塗る → まずはバルブコア付きで加圧 → ダメならコアを外して加圧 → 「ポンッ」と座ったらコアを戻してシーラント注入。この流れでほとんど解決できます。低圧運用も強化フックウォールのおかげで安心度が高いです。
_________________
座りやすさを底上げする2つのアイテム
1) Muc-Off Big Bore(ビッグボア)チューブレスバルブ
- 高流量のストレートスルー構造で、一気にエアが入りやすい。
- インサート併用時も空気経路を確保しやすい設計。
- 初期加圧でリードイン→ビードシートに“スッ”と登り、座りが速い。
2) Bontrager High Flow バルブアダプター
- 着脱式コアを外して代わりにこれを取り付けるだけで高流量化。
- フロアポンプでも最初の「ポンッ(ビードポップ)」に届きやすく、日常整備で扱いやすい。
- 使い方の詳しいレビュー:こちらの記事
- ポンプヘッドの相性に注意(一般的なクランプ式が使いやすい)。
7. 実用ディテール:幅・空気圧・インサート・サス
- 推奨タイヤ幅:2.4 / 2.5 / 2.6インチ(内幅29mmに合わせて設計)。
- 空気圧の目安(体重70–80kg/タイヤ幅2.4–2.5”):前20–23psi、後23–26psi。1–2psi刻みで調整を。
- インサート併用:低圧運用との相性良し。トラクションを活かしつつリム打ち防止。
- サス設定:しなやかさが増えた分、リバウンド調整が必要になるかも。
- 最大空気圧:50 PSI(ただしタイヤ指定を優先)。
- フリーハブ:標準はSRAM XD。MicroSpline/HGは別売対応。
最終的な乗り味はタイヤのケーシング剛性や路面状況で変わります。ホイールはベース、味付けはタイヤと空気圧。そこがMTBの面白さです。
8. 保証とサポート:生涯保証+Carbon Care
高価なカーボンホイールを安心して使い倒すにはサポートも重要。Bontragerのカーボンホイールは生涯保証に加え、購入から2年間は走行中の破損を無償修理/交換するCarbon Care Wheelが適用。さらに30日満足保証も付いています。強気に走れるのは、こうした安心材料があるからです。
9. 西村の所見(未試乗の推測)
旧Line Pro 30を使っていた身として言えるのは、とにかく「壊れない頑丈さ」に助けられたこと。表面に傷はついても致命的な割れはなく、長年使えました。トレックユーザーに限らず検討する価値があるホイールです。
新作はそこに縦のしなやかさを意図的に足してきた、と感じます。縦で刺さらず、横でブレず、駆動は遅れない。この三拍子が揃えば、快適な速さ=持続する速さに直結するはず。試乗レビューは、実際に購入してからのお楽しみ(完組か手組みか、まだ悩んでいます)。
10. FAQ
Q. しなやかさは「柔らかいホイール」という意味?
A. 違います。ここでいうしなやかさは縦方向のコンプライアンスのこと。衝撃を一瞬で止めず、短時間に受け流す性質です。一方で横方向は“横剛性(ライン維持のしやすさ)と耐久性”をキープする設計。オフセットスポークとスポーク周りの局所補強によって、横のヨレや割れに強くしています。
Q. Rapid Drive 108のメリットは?
A. 108ポイント(約3.3°)で噛み合うため、ペダル入力の「遅れ」が出にくい。テクニカル区間で特に効果的です。
Q. TLRのセットアップは難しい?
A. いいえ。広いタイヤウェル+なめらかなビードシート、さらにリムストリップで初期から空気が密封しやすく、フロアポンプでも座りやすい形状です。石鹸水やブースターを使えばさらに安心。
Q. 旧モデルから買い替える価値は?
A. 旧来の強さに、前+13%/後+11%のしなやかさを加え、「集中が続く」方向へ性能を振ってきたのが新作の価値。長いセクションで差が出るはずです。